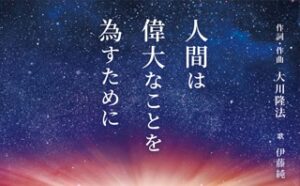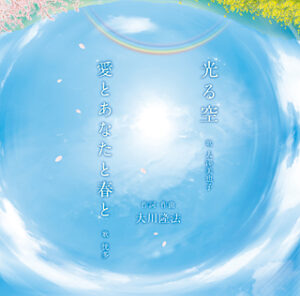原曲「光る空」体感研修①
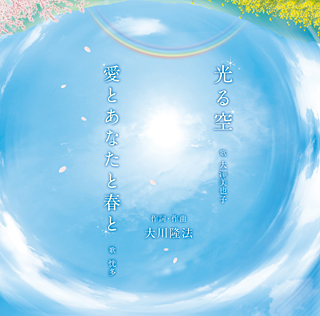
2024年4月24日 四国生誕館
A 一回二回、三回と聞いていくなかで、印象が変わって来たなと思った、
一回目聞いたときは、主が過ごされた青春の時間の一部を感じさせて、見させていただいているという印象だったのですが、幽体離脱をしている情景を書いていて、そして実らない恋についても描かれていた詩でもあると聞いて、主の透明な愛が二回、三回と聞くうちに深まっていったなと思いました。
仏が創られた世界の美しさを書いてくださっているのだなと思いましたし、この世はすべて移り変わっていくけれど、主はその時間を超えて残そうとされているので、私も一瞬一瞬を大切なものとして魂に刻んでいきたいなと思いました。
人を愛する時には総裁先生のように吹き抜けていく愛の風、透明な愛で人を愛していきたないというのを詩で学ばせていただきました。
見返りを求めない愛というのがこの詩に描かれていて深いなと感じました。
B 神の目からすると世界はこんなふうに見えているんだなと先ず思ったのですが、逆に、主からあなたの目にはどんなふうに見えているんですかと問いかけられている気がして、自分の心を探ってみたら、闇のほうが強く見えていると感じたんですね。
どっちかというと、人生の苦しみの方を強く見るような傾向があって、昨日、飛行機で来たんですけど、そのときに、最初雨が降っていて、光る空なのに雨が降ってるなと思ったんですけど、離陸して雲を突き抜けた後は、光が出て青い空がパーッと広がって、光る空だと思って。
こんなに主の光りが降り注いでいるのに、青空がこんなに愛で満ち満ちているのに、何で自分は雲の下にある雨のほうばかりを見ているんだろうって涙が止まらなかったんです。
厚い雲を突き抜けた先にある美しさまで、自分は見れていないという気がして、仏陀の説かれた四苦八苦の苦しみばかりに目が行きがちで、仏陀とヘルメスという両輪があるので片方だけの見方じゃバランスがよくない、苦しみの先にある美しさというところまでいけるように、原曲を重ねることによってバランスを修正していける自分になりたいなって思いました。
本当の世界はもっと自由なんだよ、何でもできるんだよって、肉体という家にばかり閉じこもっていないで、たまには外に出てみようよ、出れるんだよと言われている気がしました。
C この歌が凄く好きなんですけど。絵が動き出す。
先生の手によって命を与えられて、何気ない麦わら帽子とか、石垣とか、古城とか動かないものでも、石とかでも本当に美しくて動きだしそうで、風でさえ実態を持っている。
すべてに山川草木悉有仏性、先生の目から見たらすべてそうで、それを原曲を通して垣間見させていただいて、気づかせていただいて、ありがたいなと。
巡礼に行かせていただいて、すごく良かったです。原曲とセットだととてもいい。
A オープニングの映像に、主の若いころの映像が出てきて、凄い感動しました。主が過ごされてきた愛する地というのがすごく愛おしくなって、ずっとここで研修を受けていたいなと思いました。
C 生誕館、来るたびにどんどん好きになって、また来たい、また来たいになっていく。もっと、皆さん来てほしいな。
B 最後の大地に落ちるって、肉体に戻るってことですかね。
幽体離脱をしていて戻る。また、不自由な肉体に戻らなきゃみたいな。でも、使命を果たすには肉体という手段が必要なので戻らなくちゃと。
A 講師が途中で、「小さなメルヘン」の話をされていたんですけど。愛を与え続ける少年と、その愛に気が付かない少女というお話があったので、また、あとでゆっくり読みたいと思いました。
原曲はミニ説法であると、講師が最初に解説してくださったんですが、本当にこれ説法だなと感じまして。
どこまでも主のお言葉を参究できるなと感じましたし、これが高校時代に書かれていた詩だというのに驚きました。このような時から悟っていらっしゃったのだなと。
C 昨日、「あるコオロギの願い」を受けたけど、あれは中学生の時、先生の詩は深い。
B さっきの川島特別支部に飾ってあった、中学のころに書かれた先輩に向けての言葉、あれ見ても何歳の人が書かれた詩なんだろうと。
映画の二十歳に還りたいの「老齢で二十歳に見えない」みたいなせりふがあったけど、そんな感じ。
C コオロギには人間の晩年の気持ちが書かれている、中学生が書くとかね。
B 早熟すぎて当然周りは全然ついていけない。
言ってることは正論なんだけど、こんな子供に言われたくないみたいな感じじゃないかな。
C 成長の角度が凄いですよね。霊的なパワーでそんなになったわけじゃなくて、努力精進、努力精進で積み上げて来て生きてきた先生、君たちもこうやってできるんだよって道を示してくださってる。
先生のお姿を見させていただいて、少しでもついていけたらなって思います。
A この研修の前に「El Cantare in Kawashima」を聞かせていただいたんですけど、お兄さんのほうが出来る人で、先生のほうは平凡な男の子というふうに両親に見られていたと言われてるんですけど、その中で、人が三年かかるところを十年かけてやっていこうと小学生の時に決意されている。
その思いを今でも持ち続けられているから、人と少しずつ違ってきて、人を導く人になろうとしているから学び続けていて、平凡からでもそこまでなれるから頑張っていきましょうって励ましの言葉もいただいている。
その主のお姿に続いていきたいし、平凡な自分というのを自覚して人の何倍も努力していきたないと思いました。
B 普通の人だったら、都会にもまれて、ビジネス社会にもまれて、純粋さが失われていく人が多いと思うんですけど、その頃に少年の気持ちを保ったままというのが凄くて、周囲の色に染まらない凄さというのがあるなと。少年の心は持ったまま、でも努力は続ける。そこ凄い!
C そんな純粋な心を持ち続けて、あの大変な中を生きていくって。この世的に染まるのなんて簡単だから。
A 普通、染まっちゃいますよね。
C 頑固に染まらないじゃなくて、さわやかなんですよね。
B 一つ一つはすごく素朴なというか。ありふれているというか、素材としては誰でも目にしたり、体験するようなもの。
この曲に限らずですけど、誰でも知ってるものが材料なんですけど、それを使って超一流のものを創る、与えられている料理の材料はありふれた材料だけど名シェフで凄い料理を創る。
一つ一つで見ると特別なものではない。仕上げるところが凄い。
C 詩が先で、曲があとですよね。
A 曲もさわやかで、すっと入ってくるような。
C 最初のほう、先生が楽しそうに歌ってらして、私には楽しそうに感じられた。
A 先生が情景を描いて歌ってらっしゃるような感じでした。
※法談はいろんな話しが出るので、あくまでも個人の意見であり感想です。こちらで適宜編集させていただいています。