原曲「I Love New York」体感研修②
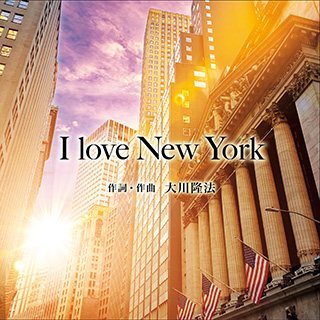
2025年3月7日 渋谷精舎
A この歌詞の中で「先生のその自信の源がどこにあるか」って語られているから1番気になって。
この曲4回聞いてるうちに先生の経験されてることと自分の経験なんですけど、女性なので仕事と家庭とのバランスの部分で、特に家庭の課題が多かったんですよね仕事より。
ただニューヨークで語られている感じは、仕事してる時に私も海外の人との接触が多かったからすごくわかる感じ。その大きい白人が怖いじゃないけど、そういうのもなんかわかる感じがして、カルチャーをすり合わせていく難しさを感じたことを思い出したんですよ。
B 海外に行かれていたんですか?
A 行ってたんじゃないんですけど、私ボリショイバレエのところにずっといたんです。
B そうだったんですか。ボリショイといえばロシアのバレエ団。
A 別にロシアに行っていたわけではないんですけど、そこの先生との接触がずっとあって。まだ20歳超えてたかなぐらいの頃の話なので、それこそ向こうは英語も分からないで来たんですよボリショイの方。
当時はソ連だったから英語が喋れないロシア人いっぱいいたんですよ。こっちはロシア語なんか尚更分からないじゃないですか。
それで意思疎通の難しさとか教えられたり、表現しなさいってあるからボディランゲージだけでもないし、言葉も分からないと結局分からないとこもあるしで、結構悪戦苦闘した頃を思い出したんですよね。
あと、その競争の部分、海外の方のスタイルが良かったので競争の土俵に乗れない面とかがあったりとか、こんなのがプレッシャーになったり、コンプレックスになったことを思い出しまして。
だからこの競争の感じはニューヨークではないですけど異文化との接触の難しさを思い出しました。
B ボリショイバレエはバレエ界では世界のトップだから、そういう世界のアレを見たのですね。
A まあね、だから、そんなのちょっと思い出して。確かに競争だから、でも、ちょっと変な言い方ですけど、この商社での男社会の中での女性ももちろんいたと思うんですけどね、だけど、なんかそういう感じ。
ただ私が関わっていた世界って意外に男社会だったのかなと思ったりとか。家庭の問題は全然また別なんですけど家庭で起きる問題ってちょっと異質。
やっぱ家庭と、中の受動性から来る母親とか自分の育った環境とか、そういうものから来るから、また違っていて全然異質なものを同時並行させた自分がいたのを思い出して、その当時を思い出しちゃった。
B 悟りへの道と、その世界の競争の中での厳しさと両方みたいな?
A 両方同時に走っていたなっていうのを思い出しちゃって。でも、そういう時って「確かに記憶に残るんだな」って思って、その期間もやっぱり1年ぐらいだったんですよ。
だから「短期間の中での圧縮した何かっていうのは転機になるのかな」ってこの曲で1番思ったんですけど。
B 私も女性だから、まず思ったことない、こういう世界で生きるみたいなところ。ただ家族が競争社会の人で、そういう戦いを横で見てきた感じがあるから男の人は大変だなと思いつつ。
歌詞の中で神の試しが「お前に強敵をぶつけるだろう」っていう言葉が私は1番強烈で、強敵来た時に逃げると思った。そういう人って苦手っていうか、女だから逃げちゃうのかな。あんまり戦いの土俵に乗りたくないみたいなとこあるから。
でも仏弟子として主の願いを実現するために、自分はミクロの地域社会で、主の願いに合わせて最高の自己を差し出せるように、日々どうしたらいいかみたいなことは自分なりにはやろうとしてきてるけど、でも、やっぱ強敵みたいな苦手な人って出てくるじゃないですか。
それが、理解しようとしても理解がなかなかできないことが長く続いたなと思って、うん。
あと「己自身を知ることが」とは、その自分の仏性や真理の確信とかなのかなと思って。それは小さい自分の世界の中でも探求し続けて、正直に生きて頑張れば掴めるのかなと思って、そういうところから頑張ることがリンゴになるのかなと。リンゴにはまずなってない。
このビックアップルはニューヨークの象徴と言われてるらしいですけど、「自助論の精神」の後書きに「リンゴの例え」が出てくるんですよ。
下村湖人の「台風が来て実ったリンゴがすぐ落ちてしまうけど、それで嘆くのではなく、その環境に打ち勝つ」みたいな考え方が、先生がすごく影響を受けた思想なんですよ。
それが自助の精神の根本だと思うんですけど、「ビッグアップル」とすごい強く歌ってるから、多分ここは、日本でビッグアップルになったと、日本の頂点に立つぐらいになって、さらに世界の舞台で戦いに来たぞみたいな感じなのかなと思って、自分に置き換えればアップルにもなってないから、まずアップル目指そうとか思いました。すみません、ちっちゃいもんで、ちっちゃいことしか言えなくて。
C 私は素直に、立身出世じゃないですけども、そういう感じをすごく受けて、この時主は大悟されてるんですよね。で、「この目の前のエンパイアステートビルと自分の心のうち、どっちが本当なんだ」みたいなことを仰ってたので。
だから、2つの視点があるんですよね。「神の目を持ちながらも、現実に肉体に宿ってる自分と、この人間の苦労をここであえてしてるんだな」と。
で、人間たちの生き様を、本当ただただ努力の人ととしか見えない。私は見えないですよね。だけど「最後にかすかに微笑んで、その眼差しを世界に向けるんだ」って。これは多分「神の視点かな」と私は思ったんですよね。「ある程度やり遂げたかな」みたいな。
だから、あと神様でもやっぱりコンプレックスみたいなの感じたのかなと思って。
ここで、この白人とねえ。だけど先生が行った頃は、多分日本がすごい元気だった時代、日本で1番イコール多分世界で1番ぐらいのとこだったと思うんですよ、あの時代、ちょうどバブルの時は。
B 東大も世界のレベルの中に入ってたんですよね、あの時は。
C だから、ある意味人間界の頂点まで先生は行ってみせたっていうかね。努力努力で、ほんとただ努力だけでね。
日本の田舎から出てきて、本当特別な下駄履かせてもらえるわけでもなく「地道にコツコツ積み上げてここまで行きました」と、「こういうこともできますよ」ってことを背中で教えてくださったと私は思いました。
D 私はこの「I love New York」はすごく好きな原曲の1つに入ると思いましたね。で、遥かなる異邦人から数年でニューヨークに行って、あんな経験されたわけでしょ。
神様のスピードってすっごい。救世主のスピードって早くって、わ〜んって行って、悟って。なんか変な話だけど、ご家族のこととかも全部通して今こうなってるんだって、ちょっと納得したっていうか、すごいスピードでグワーって行かれたんだなって思ったのと。
あと、この詩を降ろされた時と過去を行ったり来たりしてるような視点がすごい変わってて、最後はもうワールドトレードセンターって、この時多分詩を編まれた時はもう壊れてないよね。
B これ歌われた時はもうないです。
D それで、そうなんだって自分でも思ったのと、あと「ジャパニーズタイガー」っていうじゃない。
B 私も同じく母親になった時虎になったと思いました。
D 私も虎だと思った。ジャパニーズタイガーってさ、タイガーっていう意味。ねえ、もう何かすごい。
A でも、なんかわかりますよね。環境のスピードと先生の心の中での変化のスピードが全然違いすぎる。心の中のスピードがもうそうなるよね。この世の時間の流れてるスピードでものは動いてるじゃないですか。
出来事的に現象的としては。だけど先生から、心の中の進化スピードって言っていいのかな、進化って言ったら元々あれなんだけど、だけどブーンみたいな、ここまでどのぐらいの距離時間で動き、ここまで持っていくかみたいな計算して動いてるのかと思うぐらいすごい。
D すごいと思ったし、これを見た時に遥かなる異邦人から数年もたってないのにね、いきなり実社会出て2年目でアメリカに行って、すごい自己鍛錬っていうか、仕事能力つけて、救世主としての力を蓄えて、どんどんやっていって、ご家族とか不甲斐ない仏弟子を抱えてウワーって行ったんだなって思った。
B そのブオーンって行ったのが、「象徴的な戦いをしなさい」って館長が式典でお話して下さったんだけど、主はやっぱその象徴的な戦いに全力投球するのがすごいのかな。
私なんか多分脱線脱線でずれまくってるんだけど、これを抑えればガーンってそれもすごいんでしょうね。
A どこが象徴かわかるのだと思う。
BD わかんない、わかんない。
D だから己自身を知れっていうのよ。
B あっそれだ。己自身を知るだよね。
D 主の偉大さ。
B 天狗ってまず己自身を知れって、「さらば、うぬぼれ天狗」そうだったよね。そこ重要なんですね。勘違いで違うレールに走っちゃって。
D 先生、すごいよね。深いし、やっぱりすごいスピードだよね。で、駆け抜けていちゃったんだよ。
A 地獄和尚の土管でボーンと発射する感じのあれですね。
B あれも先生っぽいよね。
D 先生よね。絶対
B ヤイドロンさんみたいなこと仰ってたけど〜。
D やっぱり先生よね。
B で、やっぱ使命の自覚っていうのがとても大きいじゃないですか、私たちと違って、世界を救うっていう、それがやっぱこれだけのものになっていく。
D 結局は、あーと思って、もう一度次のステージっていうんで、こういうことになっちゃったのね。
A 本当に中学生の頃の書かれた詩からして「何か悟ってるよね」って、最初。もうねあんな中学生いない。
D 私ね詩を1つ読む毎に「先生天才だ」と思うの。わかるわかる。
A わかる、自分の中学生の時、こんな事考えてない。
B 初め書いたの「老人の手」だものね。12歳で。
A 老人の手を見て何も思わない。
B そうそう。シワだらけとか。シミだらけだったとかね。
A とても詩にならない。
D 神。だから詩1つでも神様だよ。やっぱり「己自身を知る」ということが最後の自信の根源になるんだね。
B 天狗から抜け出すためにも必要ね。
A 究極のぐるぐる思考ですね、アレって。出る気ないもんね。だって本人、出る気ないもん。
B ないもんね。人を使ったりすることはするけど、自ら変えようとは絶対しないもんね。
A 自分がグルグルしてるの分からないまま、ずっとグルグル。でも、なんか動いてる気持ちにはなってるらしいっていう。わかります?
B 笑笑。なるほどね。
A 動いてる気分にはなってはいる。
B 妄想の世界の中でね。
A でも、出口なし。
B なんかワールドトレードセンターのてっぺんで軽やかに微笑んでますっていうのが、「天才で、ごめんなさい」の天窓を突き破って登っていくとか、「ドラゴンハート」の川から垂直に天に高く登るみたいな、そことやっぱ重なる。
D 重なるよね。
A 垂直のね。
B だって、その世界の中心の地で宇宙人たちも注目するような舞台で、そこで勝ち抜くってね。
D だってさ、遥かなる異邦人から、数年でこんなことやってらっしゃるなんて考えられないよ。あの詩自体は小説は大学時代、まだ悶々としてて卒業して、商社に入って2年目で。
B だから自分を変えてくれた地だからアイラブニューヨークで好きな地なんだね。それまでだったら悶々としていたけど、ここで戦いに突き出されて。
D 小説から見たら全然違うよね。内面を見つめてて、外に向かって力をまたつけてくっていう感じなのかな。心を耕して、この世的な力もつけて。
B お父さんとお兄さんが塾開いて借金抱えてる時。
A それもあって、仕事に就かれたんですよね。
B だから学者の道を諦めて商社にね、呼ばれたとこに行って。
A でも、なんかつくべき先生も見当たらなかったという話もあったんですよね。
B その中で、大学で経済やってなくて金融界の中心に行くってすごいよね。
A それもあんまりまだわからないうちにね。
D 教団を回してくっていうか、その力を。だって金融もわからなかったら大きく教団できないもんね。
B 無借金経営だものね当会もね。
A でも、この頃に詩を書かれたりとかして、心のバランスをとってたというのは、なんかはちょっとわかる気がする。
B わかる。普通まみれちゃう。
A で、ちょっと変な言い方だけど霊障になっちゃいそうじゃない。
B なると思う。なるし、何かに逃げ場を作ってね。周りの人は女に走って商社って。
A お酒にも付き合わされてるし。
B お酒も2時半まで。
D このニューヨークの最初先生がお住まいになった所が映った時にものすごい感動したね。
B 残っているのが嬉しかった。なんか今ふと思ったんですけど、キングコングって白人の美女を救うから、それで出たのかな。白人の金髪ビジョンが怖くてと。
A 自分は救うほうって。
B そうそう、そうやってられるかって。それちょっとかけてるかな?キングコング。
D でも映画の中でさ、先生って割と小柄じゃない。だから大きい女性とかさ、やっぱあったんじゃないかな。
B 日本人はそういうコンプレックスがありそうだよね。体格の。
A アメリカ人って、横も縦も結構大きいからね。声も大きいからね上からワーと喋り出すと。だから大きいし、キレッキレの女性にワっーて言われて、えっ〜ってあるよね。
B 日本人と全く違うもんね、理屈で全部くるし。
A そうそうキレキレのわからないじゃない。
D 英語って主語と動詞と目的語とか主語と動詞と補語だからすごいわかりやすいけど文って最後まで行かなきゃわかんない。曖昧だからさ。いや文化がやっぱり違う。
B 全然違いますもんね。
A 先生がどちらのタイプかというと先生ご自身はキレキレだから慣れればこちらはいけるかもっていう感じはするけど、最初は日本の会社の雰囲気と全然違うと思うから。
日本、やっぱり妖怪的じゃないですか。それよりはもしかしたらあれだけど、最初はびっくりしましたね。きっと女の人も全然臆しないでバーと表出てきて言うから。
B うーん、それはあると思いますよね。でも正当に評価するっていうのもありましたよね。
A そうそうそう。
B あなたがする仕事が違うとかね。
A そうそう。だから、きっと両面見てこういう感じなんだっていうことなんでしょうね。
B 結構、苦しみもちょっと現れてるかなと思ったのが、ジャングルの死闘が繰り返されるって、まるで「ヘルトゥヘル」の地獄が終わっても終わっても繰り返される感じ、苦しいよね。
D 仕事も大変だった。そうそう、毎日。
B 仕事も勉強も。
D 銀行行って、お酒も飲まなきゃいけないし。
B お酒飲むのは辛かったでしょうね。付き合いね。競争社会の人って睡眠時間も少ないもんね。
D いや、体力ないとできない。
B いや、体力最後勝負だから。レジメの中で「あと30年戦って、体を鍛え、頭を鍛え、心を鍛え続ける」っていうので、やっぱり体と頭と心、全部セットでやんないとダメなんだなって。
A そうですよね。うん、きっと。この心を鍛えるっていうのが、そういう世界で1番疎かになりがちなかんじ。頭は多分鍛える体力がないと続かないとみんなすぐ思えるけど、「心を鍛えることが重要だ」って、ちょっとピンと来づらい状況にはなってるのかな。だから野獣だね。
B 野獣だねえ〜。先生ってニューヨーク時代は体力はどうやっていたのだろう。
D でも元々剣道やってたりとか体力あるんじゃないの。
B いや、そんなことない。先生、なんか〜
A 寝て起きれなかった。会社が休みの時に寝たら起きたら夕方だった事とかありました。
※法談はいろんな話しが出るので、あくまでも個人の意見であり、感想です。こちらで適宜編集させていただいています。


